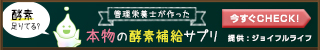毎年、5月5日に行われる行事といえば「子どもの日」。主に男の子のお祝いとして知られていますが、子どもの健やかな成長を願う日として女の子も含めて子どものたちみんなのお祝いをすることも増えました。

2020年04月30日 更新
【保育業時】「こどもの日」の由来をひとまとめ(こいのぼり・かしわ餅・ショウブ湯)
「こどもの日」の由来をまとめました。こいのぼりやかしわ餅、ショウブ湯の意味を解説します。実は知っているようで知らなかったことがあるかもしれませんね。伝統行事は子どもたちに大切に語り継ぎたいものです。保育業時や製作の導入に話すといいですね!
保育Willに参加して
造形コンテンツゲット無料会員登録
子どもの日の由来を知っておこう
いかがでしたか?


「端午の節句」とも言われています
子どもの日は「端午の節句」とも言われています。これは、昔ながらの子どもの日の呼びかたです。「菖蒲の節句」とも言われてきたそうですよ。
ショウブ湯の由来
子どもの日はショウブ湯に入る風習があります。菖蒲は「勝負」や武士を尊ぶ意味と同じ読み方であることと、菖蒲の葉のかたちが剣に似ていることから男の子の祝いに使われていたそうです。ショウブ湯に入るのは、その名残りなのかもれませんね!
こいのぼりの由来
かしわ餅の由来
中国の黄河上流には登竜門と呼ばれる難所があり、そこを登り切った魚は竜になれるという登竜門伝説があります。 「こいのぼり」はこの登竜門伝説にあやかって、子どもが様々な困難に打ち勝って大成する立身出世するよう願って飾られます。
かしわ餅をつつむ柏は、昔から神聖な木と言われてきました。新芽が出ないと古い葉が落ちないので「跡継ぎが途絶えない」という「子孫繁栄」の象徴とされ、端午の節供の縁起の良い食べ物として広まりました。
■菖蒲と花菖蒲は違う
菖蒲ときくと、ふと思い出すのは花菖蒲ではないでしょうか?実は、端午の節句のショウブ湯に利用されるのは、サトイモ科のショウブで、ハナショウブとは別の植物です。
子どもの日の由来をまとめてご紹介しました。いかがでしたか?こいのぼり、ショウブ湯、端午の節句など、どんな由来だったかな?と振り返ってみる機会になればうれしいです!
■こいのぼりの色について
昔は真鯉(黒い鯉)のみであげられていましたが、明治時代頃から真鯉(まごい)と緋鯉(ひごい)であげるようになりました。昭和頃からは家族を表すものとして子鯉(青い鯉)を足すようになったそうです。最近では緑やオレンジといった、より華やかな色の子鯉も定番になってきました。
鎧や兜を飾る理由は?
子どもの日に鎧や兜を飾るのはなぜでしょう?これは武家社会から生まれた風習です。身の安全を願って神社にお参りするときに、鎧や兜を奉納するしきたりに由来しています。現在は鎧兜が“身体を守る”ものという意味が重視され、交通事故や病気から大切な子どもを守ってくれるようにという願いをこめて飾ります。





Lineでお友達登録するとお役立ち情報を配信します!
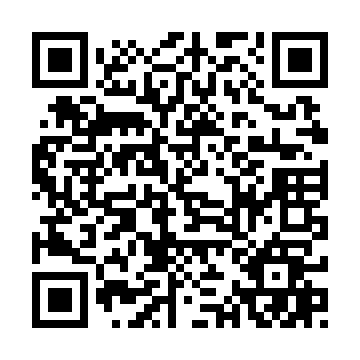
この記事が気に入ったら「いいね!」しよう
保育士ライフスタイルメディア|保育Willの最新情報をお届けします